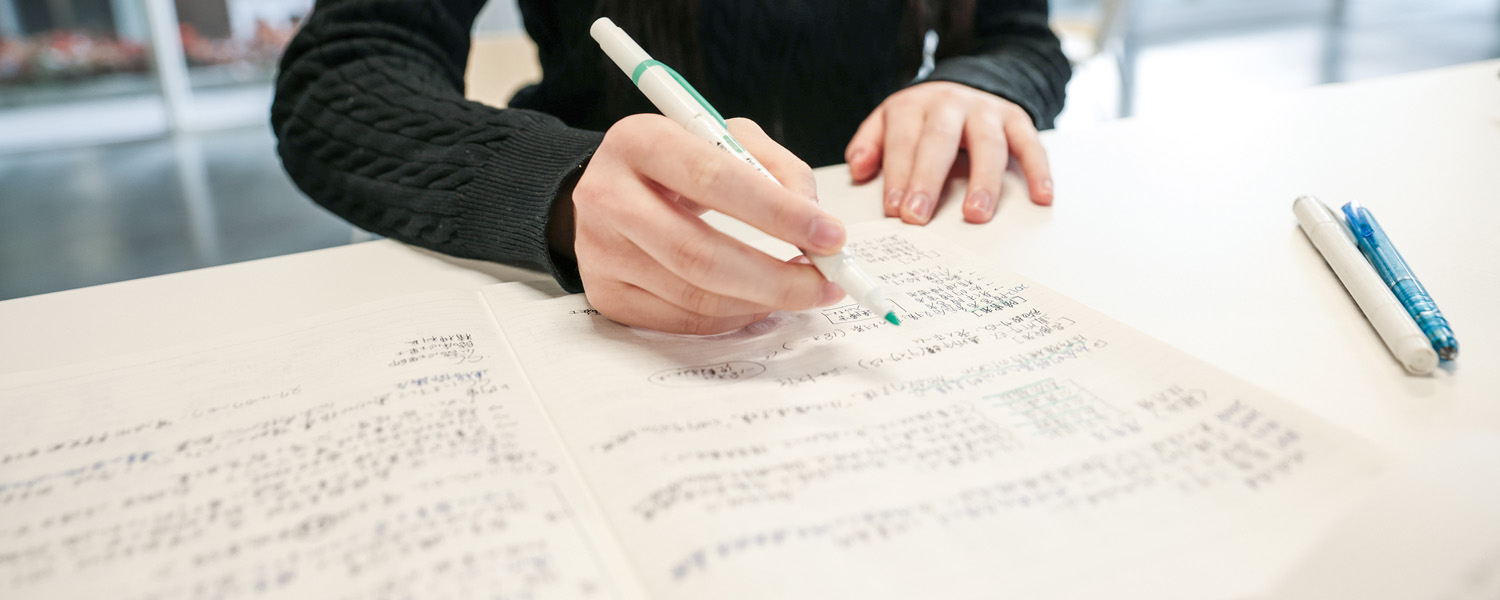Need Help?
学科紹介
心理学科
人と人とのつながりを深く理解し、共に行動する人間を育む。
Projects プロジェクト紹介
▼解決を目指す「社会課題」
コミュニケーションの希薄化
地域の人々と心を通わせ
コミュニケーションを再生する


渡邊 莉那さん
2年生(京都府 龍谷大学付属平安高等学校 出身)

南 穂香さん
2年生(大阪府立住吉高等学校 出身)

馬淵 美早季さん
2年生(大阪府立三島高等学校 出身)
心のつながりを探究し社会に力を生み出す
心理学プロジェクト社会連携演習は、心理学部での学びや経験を社会に活かすことを目的とした実践的な授業です。京都府内の産官学セクターと連携しながら、心のつながりやコミュニケーションの重要性を深く理解し、他者とともに行動・共創する力を養います。このプロジェクトのポイントは、私たち学生が発案するアイディアを軸として、地域社会のニーズに応じた企画を検討する点にあります。フィールドワークによって地域の実態を把握し、目標設定からタスク管理までの工程を自分たちですべて行います。そして、単なる授業の枠を超えて主体的に行動し、身近な社会で心理学の知識を実践していくのです。2024年度の実践の場は、高齢化と人口減少による衰退に悩む深草商店街です。「ふかくさ100円商店街」の企画・実施をとおして、心理学の視点から、「コミュニケーションの希薄化」という社会課題の解決策を探ることになりました。
商店街で感じた温もりに対話の大切さを実感
かつては地域コミュニティの中心として栄えた深草商店街も、今や空き店舗が目立つ閑散とした状態です。来訪者の減少という深刻な課題に対して、地域の方々と対話を重ねながら、心理学的な視点で分析しました。そこから見えてきたのは、単なる商業の衰退だけではなく、 人間関係の希薄化という問題でした。フィールドワークを通じて実感したのは、地域ならではの温もりです。商店主の方々はとても親切な方ばかりでした。魅力ある方々の温もりある接客、何気ない会話こそが、商店街で買い物をする良さではないでしょうか。スーパーだけですべて完結してしまう時代だからこそ、人と人とのつながりが大切なのだと改めて気づかされました。私たちが企画した古本・栞サシェの販売、栞づくりのワークショップでも、人との対話とつながりを重視し、誰もが気軽に参加できる雰囲気づくりを心がけました。
商店街の価値を共有し人々の交流の場を創造する
当日のワークショップでは、六種類の香りから好みのものを選んでもらう過程で、参加者の世代や価値観にあわせたコミュニケーションを実践しました。子ども連れの家族の参加者から好評を博す一方、対話を通じて「近くに住んでいるけれど普段は商店街を利用していない」と残念な声が聞こえてきたことも事実です。今回のイベントをきっかけに再訪してくれる人が増えれば、どの店舗ももっと活気づくでしょう。私たちのような学生が率先して足を運び、SNSなどのツールを介してその魅力を広めていくことも、商店街に賑わいを取り戻す手立ての一つとなり得るかもしれません。買い物の場として終わらせず、地域コミュニティとして活用していくことで、商店街の可能性が広がるのだと強く確信しました。この新たな気づきは、私たちが提案する解決策の重要な基盤となっています。
心理学的なアプローチで社会課題の解決をめざす
今回のプロジェクトでは、単なる商品販売ではなく、心理学的アプローチによる地域コミュニティの再生という視点を大切にしました。販売やワークショップで実践した「寄り添う」コミュニケーションを通じて、心理学の専門知識は机上の学問ではなく、地域社会の課題解決に直接活かせることも理解できました。また、ターゲット層の心理分析や具体的な運営方法の検討を重ねるなかで、論理的思考力も磨かれたと感じています。どこか他人任せで自分の意見を積極的に発信してこなかった私たちも、この経験を通じて自分の意見に自信がもてるようになりました。何よりも、これまで他人ごとだと思っていた社会課題を、自分ごととしてとらえられるようになったことは大きな成長です。グループワークによって培われた主体性と実践の場で得られた対人援助の手応えは、社会課題と向き合う原動力となるに違いありません。
SEE MORE
▼解決を目指す「社会課題」
データに対する倫理的配慮
心理学と工学的な知見と技術の融合による学びが
学生たちの可能性を広げる


藤原 直仁教授
[専門分野]生理心理学

崔 舜星講師
[専門分野]システム数理
心理学とデータサイエンスの融合で広がる学びチーム教育がもたらす新たな可能性
心理学部における「心理学とデータサイエンス」の授業には、重要な教育的意義があります。心理学が本来もっている統計的・科学的な側面を強化するとともに、現代のデータ活用の視点をプラスすることで、学生の可能性を広げていくのです。特徴的なのは、心理学とデータサイエンス、それぞれの専門教員によるチーム教育である点です。心理学と工学の融合により、倫理的配慮や適切なデータ収集といった心理学特有の観点と、プログラミング言語「R」によるデータ分析や可視化などの工学的なスキル、両方の修得が可能となります。また、統計的有意性の本質的な理解や、データのもつ限界についての認識を深めることで、安易な一般化を避け、少数派の存在も考慮に入れた、より深い考察力も養われるでしょう。心理学は伝統的に統計を重視してきた分野です。その強みとデータサイエンスの知見を掛け合わせることで、より豊かな学びになると確信します。
社会に貢献できる確かな判断力と伝達力を養成心理とデータを結び、キャリアの幅を広げる
学生に身につけてほしいのは、自分で考え、それを他者に伝える力です。データに基づく意思決定は重要ですが、それは単なるスキルに過ぎません。統計的な数値の背後にある本質を理解し、実社会のなかでどのような意味をもつのか分析する力が求められるのです。情報は扱い方によって時に人を傷つけます。重要なのは、データを扱う際の倫理的配慮や統計的判断の限界を理解したうえで、適切な意思決定ができる力です。心理学の専門性とデータサイエンスの知見を組み合わせることで、社会課題に対して独自のアプローチができる人材となりうるでしょう。この授業で得られる知識やスキルを活かし、カウンセラーに限らず、データ分析やマーケティング、研究職など、多様な分野で活躍してもらいたいと考えます。それは、心理学部の学びに新たな価値を見出すことにもつながるはずです。総合的な判断力を備え、社会に貢献してほしいと期待しています。
SEE MORE
▼解決を目指す「社会課題」
心の悩みに対する支援
多角的視点で広がる心理支援の可能性
専門家が果たすべき役割を考察する


上森 友彩美さん
2年生(滋賀県立膳所高等学校 出身)
日常生活に不安や生きづらさを感じる人へ個別最適な支援のあり方を考える
公認心理師の職業責任や倫理を学ぶなかで見えてきたのは、現代社会で増加する「生きづらさ」という課題です。めまぐるしく変化する社会では、多くの人が日常生活に不安や悩みを抱えています。この課題は決して他人ごとではなく、誰もが直面する可能性のある身近な社会問題です。授業内の事例検討やグループディスカッションを通じて、そうした方々への心理的支援のあり方を深く学びました。特に印象的だったのは、ある支援事例に対して多角的な視点から最適なアプローチ法について考えたことです。学生間で活発な意見交換を行い、自分だけでは気づけなかった新たな視点が得られました。自分の意見を共有することで考えが整理できるほか、それが相互理解につながることも身をもって理解しました。実際にクライエントの悩みに向き合う際も、多様な角度から考える必要があると実感しています。座学だけでは得られない実践的な学びの機会でした。
心の健康を支える専門家として自分に何ができるかを問い続ける
公認心理師は、支援を必要とする人に寄り添い、味方であると伝え続ける必要があります。それは単なることばではなく、一つひとつの行動や発言に表れるものだと理解しました。国家資格である公認心理師は、国民の心の健康の保持増進に貢献するための職業です。社会に対してどのような責任を担い、何を期待されているのかを自分に問い続けなければなりません。解決策として考えたのは、心理的支援の充実と、生きづらさを抱えている人がたくさんいると社会に周知することです。さらに、さまざまな側面からクライエントに最適な支援を考え、人生全体を見据えたアプローチも重要です。公認心理師として目の前のクライエントの人生に大きな影響を与える責任を常に意識したいと思います。「寄り添う」ということばの真の意味を追究しながら相手の心を汲み取り、社会全体の心の健康に貢献できる専門家になりたいと思います。
SEE MORE
Seminars ゼミ紹介
牧 久美子 ゼミ

不登校と心のケア
自らの経験と心理学の学びを活かし
傷ついた子どもの心に寄り添いたい
葉田 成道さん
心理学部 心理学科 1年生(香川県立観音寺第一高等学校 出身)
心理学の本質を学び、心理的支援のあり方を考える
悩みがあり、スクールカウンセラーの方にお世話になった中学時代の経験から、人の心に寄り添う心理職に就きたいと考えるようになり、心理学部への進学を決意しました。実際に心理学を学んでみて、これまで耳にしてきた臨床心理学や教育心理学以外にもさまざまな分野があることがわかり、学びへの興味と意欲は高まる一方です。現在は「対人支援」をテーマとする牧ゼミに所属し、不登校や心のケアに関する研究に取り組んでいます。研究を始めて特に驚いたのは、カウンセリングを必要としていても、対面での相談が難しい人が少なからずいるという現実でした。この新たな気づきは、カウンセリングの結果ばかりを重視していた私にとって、心理的支援のあり方を考える大きな転換点となりました。
これまでの学びを土台に、より専門的な分野に挑む
ゼミではグループごとに調査や研究を行い、他のゼミとの合同発表会に向けた準備をすすめています。牧ゼミの特徴は、明るく和やかな雰囲気のなかで、深い学びが得られることです。先生の丁寧なアドバイスのもと、メンバーと協力しながら情報収集や資料作成に取り組んでいると、新しい発見も多々あります。また、ゼミで学んだファシリテーター・スキルをグループディスカッションで活かしています。今後も臨床心理学や発達心理学、教育心理学への学びを深め、将来はスクールカウンセラーとして、心に不安や悩みを抱えている子どもたちの支援に携わりたいと考えています。また、障がい者心理やスポーツ心理学など、より専門的な分野にも取り組んでいく予定です。多様な人々の心に寄り添える専門家となれるよう、これからも研鑽を重ねていきたいと思っています。
[卒業研究のテーマ(例)]
- 大学生のLGBTQ+に対するイメージについて
- 香りが心身に及ぼす心理学的効果
- 日本におけるマインドフルネスの拡大
- 震災による心理的影響の把握とケアに関する一考察
- イップスに陥る原因と克服へのプロセス
- 大学生における他者理解と共感経験について
- 大学生における幼少期の地域コミュニティと子育て観について
- 大学生におけるファッションとアイデンティティの関連性
梅野 智美 ゼミ

教育現場での人間関係
より良い関係の構築に向けて
心理学の視点から考える
菅 弥慧子さん
心理学部 心理学科 2年生(広島県 ノートルダム清心中・高等学校 出身)
第一印象を形成する、人の心理に迫る
人の心や感情に興味があり、心理学部を志望しました。日常生活と密接にかかわる心理学は非常に奥の深い学問で、集団心理の授業では、過去の自分の行動の理由まで明らかになります。心理学を学べば学ぶほど、私が想像していた以上に幅広い分野で活かせることがわかりました。私が所属する梅野ゼミは、貧困による教育格差やヤングケアラー問題、学生の不登校、発達障がいの子どもへの向き合い方など、さまざまな教育問題を扱っています。私たちのグループは「人の印象は何で決まるのか」をテーマに研究をすすめています。なかでも特に着目しているのは、初対面における印象形成です。ゼミ活動の集大成として行われる最後のプレゼンテーションに向けてインタビュー調査を実施し、このテーマに関する情報を収集しています。
異なる価値観と新たな視点が、人間的な成長を生む
インタビュー調査の結果には、興味深い発見がたくさんありました。例えば、瞬きの回数が多い人は情緒が不安定だと思われやすく、うなずきや相槌の多い人は感情的・社会的な魅力を感じる傾向にあります。人間関係を円滑に構築する方法などもわかり、私自身もコミュニケーションの取り方に配慮するようになりました。このゼミでは、自分たちで自由に研究テーマを設定します。興味のある分野を追究できるので、日々の活動にも自ずと力が入ります。また、同じ分野に興味を示す仲間とのグループワークでチームの絆も深まります。自分と異なる価値観をもつメンバーとの出会いにより、多様な視点や考え方といった新たな気づきを得ることも少なくありません。今後も人間関係やコミュニケーションに関する学びを深めていきたいと思います。
[卒業研究のテーマ(例)]
- 子どもの遊びの発生要因、環境要因
- 大学生の幸福に関する一考察
- 大学生の学校適応感とコミュニケーション能力の関連について
- 大学生の心の居場所に関する研究
- 大学生が抱く大人イメージについて
- 日常生活の心理状態と夢の内容の関係性について
- コミュニケーションの図り方の違いにおける出生順位の影響
- 養育態度と承認欲求の二側面の関係